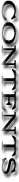栽培、海外ラン園視察などに関する月々の出来事を掲載します。内容は随時校正することがあるため毎回の更新を願います。 2024年度
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
7月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulbophyllum maxillare alba | Bulbophyllum refractilingue | Bulbophyllum gjellerupii | |
Coelogyne kinabaluensis flavaフォームのセパル・ペタルのカラーと透明感
2015年8月ボルネオ島からSabah生息種として入手した多数のセロジネの中に、花形状は似ているものの下画像左に見られる一般的なCoel. knabaluensisのもつ杏(薄い赤茶)色に対して、中央及び右画像の開花当初は透明感のある苗(淡い黄緑)色で、やがて3-4日過ぎたころから徐々に緑味が減り、黄味が増すフォームをもつ株が含まれていました。この種は毎年春から夏に開花し今年で10年になります。今回本種を取り上げたのは、セパル・ペタルのもつその透明度からです。ランの中には、例えばBulb. rugosumなどセパル・ペタルに透明感のある種は僅かですが存在します。しかし下画像に見られるように、光が前面から当たっているにも関わず、ドーサルセパルの背後にある部位の輪郭がこれほどよく透けて見える種はこれまで見たことがありません。撮影は8日です。一方、Coel. kinabaluensisのflavaフォームも公式には記録されておらず、ネットにも本種に類似するCoel. kinabaluensisの画像がありません。そうした状況からは、このフォームは稀少性が高いと思われ、取敢えずCoel. knabaluensis flavaとし、落花後には植替えを行い、株の成長を促したいと考えています。| Coelogyne kinabaluensis Borneo | ||
久々登場のデンドロビウム3種
現在(8日)、Den. bracteosum white、Den. nabawanenseおよびDen. wenzeliiが開花中です。| Dendrobium bracteosum white PNG | Dendrobium nabawanense Borneo | Dendrobium wenzelii Luzon |
Trichoglottis atropurpurea fma. flava / Trichoglottis philippinensis fma. flava
現在Trigl. atropurpureaのflavaフォームが開花中です。本種は2014年9月にフィリピンCavite州Buhoの蘭園にて開花中の花を見て入手したもので、園主によると初めて扱う種とのことでした。当サイトでの初花は入手から6年を経た2020年でした。それまでの経緯の詳細は同年7月の歳月記に掲載しています。しかしその後は毎年開花はするものの、暗紫色のTrigl. atropurpureaのネット画像に見られるような多輪花ではなく4ー5輪が続き、今回入手から10年を経て始めて、複数株で16輪の同時開花となりました。このflavaフォーム種は現在も国内外共に当サイト以外見られない希少種となっています。ここで問題なのはその種名です。フィリピンでは暗紫の花色を種名とするTrigl. atropurpurea(Rchb.f. 1876)と、花色は異なるものの形状が似たTrigl. philippinensis(Lindley. 1845)が知られています。そうした中でハーバード大学植物学者 Oakes Ames氏は、Trigl. atropurpureaとの形状の相違を認識したのか、Trigl. atropurpureaの発表から48年後となる1922年に暗紫色のTrichoglottisを、種名Trigl. brachiataとして発表しました。さらに1933年にはTrigl. brachiataはStauropsis philippinensis とは同種で変種の関係にあるとして、Stauropsis philippinensis var. brachiataとしました。さらに5年後の1938年にはL.O. Williams氏により属名StauropsisをTrichoglottis(シノニムの関係)と替え、暗紫色のTricoglottiesはTrigl. philippinesis var. brachiataとの種名に至りました。このように暗紫色種のTrichoglottisの種名は多様な経歴があります。上記の経緯を考えれば、現在知られているTrigl. atropurpureaは、Trigl. philippinensis var. atropurpureaとも云え、結果当サイトが所有するflavaタイプはTrigl. philippinensisの変種あるいはフォームの一つとして、Trigl. philippinensis var./fma. flavaともなり得ます。形状の相違が地域差や個体差の範囲内であれば、花の色合いで別種とするのではなく、最も早く発表された種名を本種名(この場合philippinensis)として、深紫色(atropurpurea)、赤紫(purpurata)、ピンク(rosea)、青(coerulea)、黄色(flava)、白(alba)など色が異なる種はその特徴を変種あるいはフォームとして位置づけ同種化することが理にかないます。しかし植物学者にとって目視による個体差から同種か別種かを判断することは難しい場合もあるようです。そうした中での当サイトのflava種ですが、Trigl. atropurpurea fma. flavaすなわち暗紫色種の黄色種とした、ラテン語とは云え色名そのままを2つ並べた種名に比べれば、Trigl. philippinensis fma. flavaの方がスマートに感じます。
下画像は左と中央が現在開花中のflavaフォームで70㎝長の炭化コルクに取り付けています。しかし株は最下部の生きた葉のある位置から最上部の葉までの長さが現在1m13㎝あり株の上半分は支持材を越えており、その越えた50㎝程の茎上に16輪が同時開花している状態です。本種は16輪が全開すると2m程離れた位置からも分かる良い香りが漂っています。花後には株を適当な位置で切断・株分けをし、それぞれ90㎝長の杉板に植替えを行う予定です。多数の同時開花を得た本種の今後の課題は、花サイズが5㎝程となるような栽培法を杉板の上で探ることになります。
| Trichoglottis atropurpurea fma. flava Philippines | Trichoglottis atropurpurea Philippines | |
現在開花中の2種:Dendrobium daimandauiiとBulbophyllum translucidum
Den. daimandauiiはボルネオ島キナバル山近傍に生息のデンドロビウムで2011年(J.J. Wood)に、一方Bulb. translucidumはレイテ島生息のバルボフィラムで 2016年(R. Bustamante, et al.)にそれぞれ発表された新種です。いずれも現在マーケット情報は僅かで、その背景としてDen. daimandauiiは生息域がキナバル国立公園域(採取禁止)に関わりがあるのか、またBulb. translucidumは、当サイトが現在栽培する本種数十株全てがBulb. leytensの発注でのミスラベル株であったように、現地サプライヤーにとっても花確認の無い株は種別判断が難しいのかも知れません。 特にBulb. transludcidumについてはIOSPEに現在も記載が無く、またOrchidrootsにおいても掲載画像は1点のみです。下画像のDen. daimandauiiは現在開花中の花で、本種は茎(疑似バルブ)が長く半下垂タイプのため木製バスケットに、一方のBulb. translucidumはこれまで炭化コルクでの栽培でしたが本種のリゾームは長く、多数のバルブが支持材を大きくはみ出しそれらが2年以上空中に垂れたままとなっていたため、この状態では今年の夏の猛暑は越えられないと思い、古いバルブを取り除き新たに下画像右に示すように先週から今週にかけて60㎝杉板に植え替えを行っています。現時点で取り付けた板数は22枚で画像はその一部です。杉板1枚当たりの葉付きバルブ数は15-20個となっています。
| Dendrobium daimandauii Borneo | Bulbophyllum translucidum Leyte | |