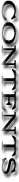栽培、海外ラン園視察などに関する月々の出来事を掲載します。内容は随時校正することがあるため毎回の更新を願います。 2024年度
2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
8月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulbophyllum gjellerupii PNG | ||
| 撮影:2023年7月 40㎝長支持材 | 撮影:2025年7月 同左 | 撮影: 2025年8月植替え 90㎝支持材 |
ところで本種名gjellerupiiですが、どう発音するのか調べました。ネット和英辞典Weblioによるとgjellerupスペルからは、1.ギィエロップ、2.ギェレループ、3.ギェレルプ、4.ゲーラロップとあり、一方でIOSPEにはその種名由来が1900年代のオランダのコレクータ名からとのことで、人名としては3のギェレルプと発音されることから、これに人名由来のラン名の語尾にしばしば付けられるiiを含めてギェレルピーが妥当かとの結論に至りました。
現在開花中の9種
ランのマーケットサイトには、しばしば販売種について’暑さ寒さに強い’との説明が見られます。栽培初心者にとってそう言われれば、その種は栽培温度を気にしなくとも容易に成長や開花が得られると思ってしまう表現でもあります。しかし当サイトではこの20年間、胡蝶蘭、バルボフィラムやデンドロビウムなど700種を超える栽培で、高温あるいは低温双方いずれの環境においても成長や開花が見られたランは2-3種程とごく僅かで、殆どがいずれか一方の環境では葉枯れや作落ちあるいは開花が見られないなどの様態が避けられない実態を見てきました。最も多い事例は入荷して1年以内に開花があったものの、その後は成長も開花も無く2-3年は現状維持が続くものの、やがて弱体化し枯れていく様態です。これは入手したばかりの株にはそれまでの環境で蓄積された体力があり、それに支えられて開花したもので、その後は栽培環境が適合しないために生じたことが主な原因です。すなわち最初の開花で現状の栽培環境で問題はないと思い違いをしてしまったことにあります。暑さ寒さに強いとの表記あるいはサプライヤーからそうした説明を受けた場合は、具体的で定量的な栽培条件(温度とその維持可能期間、夜間湿度、輝度、植付け材と容器、潅水、通風など)を確認する必要があります。 そうした中で同一ロット株でありながら高温と低温の両温室(よって高温室ではPhal. bellinaやPaph. sanderianumなど、低温室ではDen. vexillariusやDracula属などを栽培)にて成長と開花が数年続いているいわゆる例外種の一つが下画像のDen. trichostomumです。Den. macrophyllum(A. Richard 1834)については、フィリピンから入荷する種名Den. setigerum(M.A.Clem 1999)が類似種として知られていますが、下画像青色種名のリンク先に見られるようにJava生息のDen. macrophyllumの花、葉、株形状また匂い共に差異は確認できないことから、当サイトではフィリピン入荷株は先行発表のDen. macrophyllum名に統一しています。
| Aerides quinquevulnera var. flava Mindanao | Bulbophyllum lasioglossum Luzon | Bulbophyllum novaciae Sulawesi |
| Coelogyne celebensis Sulawesi | Dendrobium jiewhoei Borneo | Dendrobium subclausum Sulawesi |
| Dendrobium trichostomum NG | Dendrobium macrophyllum Luzon | Vanda mindanaoensis Mindanao |
Coelogyne usitana 花茎の最長記録?
下画像はフィリピン・ミンダナオ島Bukidnon生息のCoel. usitanaです。本種の花茎は下垂タイプで先端部に1輪花を相次いで開花しつつジグザグ状に伸長を続けるマーケットでは人気の高いセロジネの一つです。IOSPEおよびJ. Cootes氏著Philippine Native Orchid Species 2011によれば、本種の花サイズは7㎝、順次開花する花数は20輪程で花茎の長さは最長(up to)55㎝とのことです。当サイトでは2014年に本種を現地にて20株程入手し、2016年7月の歳月記にそれらの開花状況を報告しています。その中でDie Orchideeジャーナルには、花茎は葉元から最初の花柄発生位置(花軸)までの長さが30㎝、そこから1.5㎝-2㎝間隔で花軸はジグザグ状に伸び、20回程開花を繰り返して25㎝ほどに伸長し、花茎の全長は55㎝とした記述を取り上げています。しかし当サイトでの栽培実態においては、多くの株は葉元から最初の花軸までの長さは15㎝ - 18cmで花数は2-3輪と少なく、花茎全長は25㎝程である一方で、稀に花軸までの長さが32㎝、花軸のジグザグ状の伸長が半年以上続いて花茎全長は50㎝を越えた株も観測され、二つのタイプが見られるとの情報を記載しました。今回本種を取り上げたのは、下中央画像が示すように現在開花中(撮影は今月14、16日)の本種に1mを越える花茎が現われたためです。この長さはこれまで知られた中での最長記録と思われます。この株はトリカルネットにヤシ繊維マットを巻き、その上にミズゴケで根を覆った植付けとなっています。栽培は高温タイプで、輝度は中レベルです。実測によると葉元(疑似バルブ先端)から花軸までの長さが約35㎝、その先のジグザグ様態となる花軸の全長は74㎝で花茎の全長は約1.1mとなります。ジグザグの屈折点(node)は8月16日時点で43箇所あり、すでに43輪が開花したことになります。画像右はこの花茎の先端部で、次の蕾が見られるように現在も伸長が続いています。すなわち前記のサイトや書で最大とされる倍の長さとなります。開花初めの花と次の花の開花との間隔は約2週間であることから、単純計算によると43ノード x 14日=602日となり、凡そ1年半開花を続けていることになります。ちなみに本種の花サイズは9.2㎝です。花サイズ測定画像は下画像青色種名のリンク先で見られます。問題はこうした一般種とは異なる様態が栽培環境に依存した一過性のものか、この株固有の特性なのかは、下画像中央に見られるように別の葉元からの花茎での開花もあり、今後の花茎を観察し検証することにしました。
| Coelogyne usitana Mindanao | ||
Bulbophyllum kubahenseの成長II 巨大な葉サイズ
Bulb. kubahenseの葉サイズ情報については、ネット上で殆ど見ることができません。葉は葉身(葉の広がった扁平部分:blade)と、葉柄(葉身と茎あるいはバルブとを繋ぐ軸状の細長い葉元部分:petiole)で構成され、葉身のみあるいは葉柄を合わせた部分が葉サイズとされます。本種の葉サイズについては、2024年5月に実測した葉サイズ 24㎝(葉身22㎝+葉柄2.5㎝)x10㎝(幅)がこれまでに公開された中で最大と見做し、この撮影画像を本種ページに掲載しました。ところが今年5月にはそれを遥かに超える下画像に示す、葉身(blade)が38㎝、葉柄(petiole)が3㎝の全長41㎝、幅が13㎝の葉サイズが現われました。おそらくBulb. kubahenseとしては、これまでに記録の無い最長の葉ではないかと思います。こうなると一体何処まで伸長するのかに興味がわき、来年の開花期6月頃には記録更新となるように肥料も十分与え、様子を見ることにしました。| Bulbophyllum kubahense Borneo Leaf size: 41cm long: (blade=38cm + petiole=3cm) x 13cm width | ||
Bulbophyllum kubahenseの成長
2022年10月に葉付き60バルブとなったBulb. kubahenseの株分けを兼ねた植替えを行いました。その際、分割された5株のその後の成長の様子は本ページに度々報告してきましたが、今月季節外れの開花がその株の中に見られたことから、この機にと2022年から現在までの成長を改めて纏めてみました。下画像上段左は現在開花中の本種で、中央は2022年10月の植替え時の分け株の一部です。左右の株の葉付きバルブ数はそれぞれ15個と13個でした。それから1年後の株が右画像で、 2年10か月が経過した現在の様子が画像下段です。葉付きバルブ数は左が40個、右が34個に増えています。植替え当初はヘゴ板の1/3を株の伸びしろ空間として設けましたが、現在はすでにリードバルブだけでなく、分岐したバルブも支持材をはみ出し空中に浮いた状態が多数あり、また下段中央画像からはヘゴ板の裏面にも伸長し活着している様子が覗えます。このため年内には新たな植替えが必須となっています。本種の栽培環境は高温タイプとしての温度管理、また低輝度および弱い通風が基本ですが、最も重要な管理は根を決して乾かさないことです。この点からヘゴ板は炭化コルク、杉板、ブロックバーク等と比較して成長に最も有用な取付材と考え、新たな植替えも従来と同じヘゴ板とし下段画像右に見られる70㎝x15㎝のヘゴ板を10枚以上用意しました。| Bulbophyllum kubahense Borneo | 撮影:2022年10月 | 撮影:2023年11月 |
| 撮影:2025年8月 | 左画像株の支持材裏面 撮影:同左 | 植替え準備中の70㎝x15㎝ヘゴ板 |
Bulbophyllum pustulatumとBulbophyllum gracillimnumの個体差
前項に掲載したBulb. pustulatumとBulb. gracillimumには、それぞれテキスチャーや色が異なる花が多数見られます。今回その中から過去7年間の観察を通し、栽培環境(温度、輝度など)で変化することがなく株固有のフォームと確認できたものを個体差として下図に取り上げてみました。こうした同一種の中から複数の異なるテキスチャー花を得るには、開花期に合わせて現地ラン園を頻繁に訪れ花を見て選別するか、無作為に多数の株を入手した中から偶然に出会うかのいずれかになります。下図の株は後者によるもので、それなりの株数を栽培することで得られたものです。| Bulbophyllum pustulatum Malay Peninsula、Borneo | |||
| Bulbophyllum gracillimum Malay Peninsula、Sumatra | |||
猛暑の中、開花中の15種
猛暑が続く中、開花中の15種です。種名欄にある(M)マークは中温室の栽培種を示します。上段のBulb. cruentumは前項でも取り上げましたが、今回は7輪が全開したため再度撮影(8日)をしました。| Bulbophyllum gjellerupii PNG | Bulbophyllum cruentum giant NG (M) | Bulbophyllum pustulatum Malay Peninsula (M) |
| Bulbophyllum gracillimum Sumatra? | Dendrobium smilliae PNG | Dendrobium sp aff. spathilingue Java |
| Dendrobium roslii Malay Peninsula | Dendrobium fimbrilabium Sumatra | Dendrobium sp aff. flos-wanua Borneo |
| Dendrobium deleonii Mindanao (M) | Dendrobium sulawesiense Moluccas (M) | Dendrobium corallorhizon Borneo (M) |
| Dendrobium leporinum NG | Dendrobium annae Sumatra | Dendrochilum macranthum Luzon |
現在(5日)開花中のDendrobium spatulata節3種
Den. busuangense、discolor、 streblocerasが開花中です。これらはいずれも1mを越える株サイズで、それぞれが多輪花同時開花種であることから全開すると華やかです。Den. busuangenseの画像に茶色の枯れた茎が見えますが、これは今年3月に当ページで紹介した花の花茎です。今回の開花はその4か月後となる今年2回目の開花となります。下画像3種ともに5日の撮影です。それぞれの花の詳細は画像下の青色の種名のクリックで見られます。| Dendrobium busuangense Busuanga | Dendrobium discolor PNG | Dendrobium strebloceras Maluku |
大型株を含む直近の植替え8種
市場では殆ど取り扱われない程の大型株になったバルボフィラムを中心に、杉板への植替えを行っています。夏期の、特に昨今の猛暑下での植替えは好ましくないのですが、株の先端部が支持材からはみ出し長く伸びて空中に垂れたままの株も多数あり、この猛暑を乗り越えられるかが危惧され、植替えを続けています。下画像は1段と2段左が90㎝長、3段と4段目はBulb. sulawesiiの45㎝を除き、それぞれ60㎝長の杉板に取り付けられた株です。板面積の1/3は伸びしろ空間となっています。しかし2-3年後にはいずれもこの範囲を越えるサイズになると思います。これらは全て販売対象の株で、このサイズともなれば可なりの多輪花が期待でき展示会等への出品には迫力があって有効と思われますが、温室栽培にはそれなりの広さも必要となります。| Bulbophyllum whitfordii Palawan | Bulbophyllum sp aff. cheiri Palawan |
| Bulbophyllum magnum Luzon | Bulbophyllum translucidum Leyte |
| Bulbophyllum hyalosemoides Borneo | Coelogyne celebensis Sulawesi |
| Bulbophyllum rugosum Borneo | Bulbophyllum. sulawesii Sulawesi |
蘭の部位に関する用語
当サイトではランの栽培をこれから始める方を対象に、一例として胡蝶蘭のそれぞれの部位の用語や種別判定等を解説したページにリンクするタグを、2018年4月の歳月記に「原種用語のページ」として掲載していましたが、アドレスの移動でリンクが外れていることが最近分かり、これを修正しました。下記からもリンクできます。胡蝶蘭だけでなく他属にも共通する用語や様態もあり、参考にして頂ければ幸いです。| 原種用語のページ |
Bulbophyllum cruentum giant
Bulb. cruentum giantが現在(4日)開花中です。下画像上段左は2023年6月に本ページに掲載した画像で、株は葉付きバルブ数が3個で2輪が同時開花しています。画像に見られるように左株は伸びしろ面積が少なかったため花後に大きなブロックバークに植替えを行いました。その2年後となる現在、右画像の葉付きバルブ数が3倍の9個に成長し、今回7輪の開花となりました。下段は上段右のそれぞれの部位を拡大した画像です。IOSPEによると本種は花軸当たり1ー2輪とされていますが右画像では3輪が同時開花しています。ところでネットには本種について’目を背けたくなるほどの悪臭を放つ’と記載されたサイトがありますが、匂いについては2023年6月の歳月記にも取り上げ、今回も再確認しましたが当サイトの花には匂いはありません。IOSPEでも匂いマークの記載が無く無臭とされています。この2年間の成長から本種に適した栽培環境が分かったため花後には再度植替えを行い大株を目指す予定です。
| Bulbophyllum cruentum giant NG(New Guinea) | ||
猛暑の中での栽培
国内の至る地域でフィリピンやマレーシアと変わらない35℃を越えるほどの猛暑日が続いています。このため晴天日には外気温に比べ更に高温となる温室内での栽培にはエアコンによる冷房が必須となってしまいました。当サイトでは2013年、浜松に移住を決めたとき15mx5.5mの温室を4棟建てることとし、栽培するランへの潅水は水道水ではなく、温室敷地内に井戸を掘り、地下120mからの地下水としました。この深さからは1年を通し水温は季節に依らず一定で15℃となっています。夏期の猛暑時には70%遮光の寒冷紗と共に高温タイプのランを栽培する3棟の温室内では天井や壁にもこの地下水を散水することでエアコンを使用することなくこれまでは35℃を越えない環境としてきました。しかし一昨年来の気温上昇により、今年からはエアコンを稼働させなければならなくなりました。エアコンの温度設定は現在、節電を考え30℃の冷房とし昼間の稼働のみとしています。こうした温室内であっても晴天日の午前11時頃から午後3時頃までは、散水が無い場合、この広さの温室では40℃を越える日もあり、少なくとも一日1回の散水は必須となっています。これまで熱帯地域に生息するランを栽培するためには、生息域に近い保温(高温・高湿環境)つくりが主な課題でしたが、これからは高温からランを守る対策も必要となり、夏は熱すぎず冬は寒すぎないようにと、ランだけではなく植物の栽培は益々大変になってきました。
ランにおいて高温障害の発生が認識できる最初の症状は葉先枯れで、通常葉先枯れの原因の一つとしては水分(潅水)不足とも云われますが、猛暑下でこの症状が現われた場合は、病原菌による発生を除き、すでに根が枯れたり腐食してしまった結果で手遅れとなっており、作落ちは避けられません。例年に比べ葉に張りがないとか、弱々しいと思ったときには栽培温度を低くする以外解決策はありません。当サイトの栽培経験からは、中温タイプと云われる種(生息域が標高800m以上)は、栽培環境での夜間平均温度が20℃(日没から日の出までの平均値)以上では開花は得られず、25℃以上となると葉先枯れ等の作落ちが見られます。一方高温タイプでは、夜間平均温度は30℃以上が危険域となります。